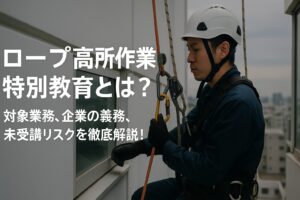床上操作式クレーン運転特別教育とは?|講習内容・費用・玉掛けとの関係性まで徹底解説!
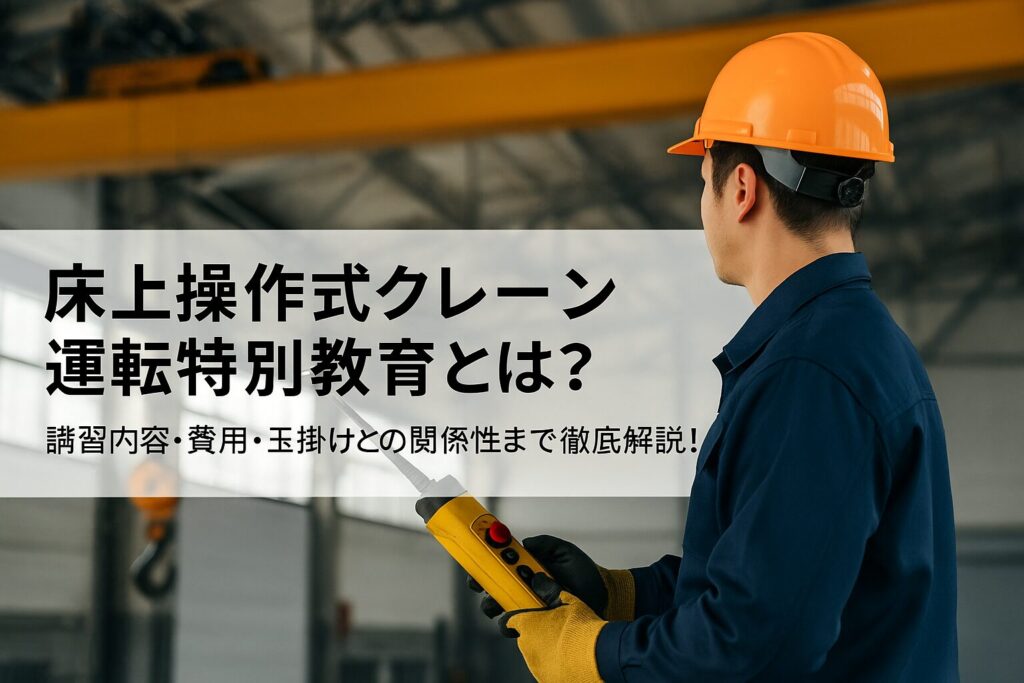
工場や倉庫などで、手元の押しボタンスイッチを操作して重量物を吊り上げ、自在に運搬する「床上操作式クレーン」。物流や製造の現場ではなくてはならない、この身近な機械を業務で操作するためには、法律で定められた「床上操作式クレーン運転特別教育」を修了する必要があることをご存知でしょうか。
「自分も操作する必要が出てきたけれど、どんな内容の講習なのだろう」「費用や日数はどれくらいかかるのか」「よく耳にする『玉掛け』とは何が違うのだろうか」など、いざ受講を検討し始めると、様々な疑問が浮かんでくることと思います。
この記事では、そんなあなたの疑問を解消するために、床上操作式クレーン運転特別教育の基本から、具体的な講習内容、費用の相場、そして多くの人が混同しがちな玉掛けとの重要な関係性まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。安全なクレーン作業者としての第一歩を、この記事から踏み出しましょう。
床上操作式クレーン運転特別教育の基本|まず知っておくべきこと
工場や倉庫で重量物を運ぶ際に欠かせないクレーン。その操作には、安全を確保するための専門的な知識が求められます。ここでは、多くの現場で必要とされる「床上操作式クレーン運転特別教育」がどのようなものか、その基本から解説します。
法律で定められた、つり上げ荷重5トン未満のクレーンを扱うための教育
「床上操作式クレーン運転特別教育」とは、労働安全衛生法という法律に基づき、事業者が従業員に対して行うことが義務付けられている安全衛生教育のことです。
具体的には、つり上げ能力が「5トン未満」のクレーンを業務で運転する場合に、この教育を修了していなければなりません。これは、作業者の安全を守り、労働災害を防ぐための重要なルールです。単なる社内研修とは異なり、法律で定められた公的な教育と理解しておきましょう。
どんなクレーンが運転できる?対象範囲を正確に解説
この特別教育を修了すると、具体的にどのようなクレーンが運転できるようになるのでしょうか。対象となるのは、つり上げ荷重が5トン未満のクレーンです。
一般的にイメージされるのは、床上で手元のペンダントスイッチ(押しボタン)を使って操作し、運転者自身も吊り荷と一緒に移動する「床上操作式クレーン」です。しかし、実はこの教育で運転できる範囲はそれだけではありません。
つり上げ荷重5トン未満であれば、
- 運転者がクレーンから離れた場所で操作する「無線(ラジコン)操作式クレーン」
- クレーンガーダー(桁)に固定されたスイッチで操作する「床上運転式クレーン」
- クレーン上の運転室で操作する「機上運転式クレーン」
なども運転することが可能です。
ただし、注意点として、トラックの荷台に搭載されたクレーンなどの「移動式クレーン」は、この特別教育の対象外です。移動式クレーンを操作するには、別途「小型移動式クレーン運転技能講習」などの資格が必要になるため、混同しないようにしましょう。
上位資格(技能講習・運転士免許)との明確な違い
クレーンの資格には、この特別教育の他に「技能講習」や国家資格である「運転士免許」が存在します。これらの最も大きな違いは、操作できるクレーンの「つり上げ荷重」の大きさにあります。
それぞれの資格で何ができるのか、下の表でその違いを確認してみましょう。
| 資格の種類 | 操作できる荷重 | 主な対象クレーン・備考 |
|---|---|---|
| 床上操作式クレーン運転特別教育 | 5トン未満 | 床上操作式、無線操作式など、5トン未満のクレーン全般。 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 5トン以上 | 5トン以上の「床上操作式」クレーン。無線操作式は対象外。 |
| クレーン・デリック運転士免許 | 制限なし | すべてのクレーンとデリック。国家資格。 |
このように、自分が職場で扱うクレーンの種類と重さを確認し、どの資格が必要なのかを正しく判断することが重要です。もし将来的に、より大きなクレーンを操作する可能性がある場合は、技能講習や運転士免許の取得を視野に入れると良いでしょう。
このように、クレーンの資格は扱う荷重や種類によって細かく分かれています。そもそも「特別教育」「技能講習」「免許」といった資格区分にどのような違いがあるのかを理解しておくと、自身のキャリアプランに合った資格を選びやすくなります。
特別教育の具体的な講習内容
床上操作式クレーン運転特別教育は、ただ話を聞くだけで終わるものではありません。安全に操作するための知識を学ぶ「学科講習」と、その知識を元に実際にクレーンを動かす「実技講習」の二本立てで構成されています。ここでは、それぞれの講習で具体的にどのようなことを学ぶのかを詳しく見ていきましょう。
学科講習で学ぶ知識(クレーン・力学・法令など)
学科講習では、クレーンを安全に運転するための理論的な知識を学びます。一見すると専門的で難しそうに感じるかもしれませんが、事故事例などを交えながら、講師が分かりやすく解説してくれるので心配はいりません。主に以下の4つの科目について学習します。
- クレーンに関する知識 クレーンの各部の名称や構造、どのような種類があるのかといった基本的なことから、万が一の事態を防ぐための安全装置の役割と機能について学びます。
- 原動機及び電気に関する知識 クレーンを動かす動力源であるモーターや、操作に必要な電気の基本的な知識を学びます。感電などの労働災害を防ぐための、安全な取り扱い方が中心となります。
- 運転のために必要な力学に関する知識 安全なクレーン作業の根幹ともいえる重要な科目です。荷物の質量と重心の関係、ワイヤーにかかる力の計算など、荷物を安定して吊り上げるための力学の基礎を学びます。
- 関係法令 労働安全衛生法など、クレーンの運転に関わる法律や規則の中から、作業者が特に知っておくべき条文について学びます。なぜこの教育が必要なのか、法律上の根拠もここで理解することができます。
実技講習で身につける技術(基本運転・合図)
学科で学んだ知識を頭に入れたら、次は実際にクレーンに触れて操作技術を習得する実技講習に移ります。ヘルメットや安全靴を着用し、安全が確保された環境で、講師の指導のもと行われます。
- クレーンの基本的な運転 ペンダントスイッチを実際に手に取り、クレーンの「上下」「東西南北」の動きを操作します。荷物を吊り上げ、指定された場所へ安全に移動させ、正確に降ろすまでの一連の流れを練習します。特に、吊り荷が揺れてしまう「振れ」をいかに素早く止めるか(振れ止め)は、重要な訓練の一つです。
- 運転のための合図 クレーン作業は、運転者一人だけで完結することは少なく、荷をフックに掛ける「玉掛け作業者」との連携が不可欠です。実技講習では、玉掛け作業者と安全に連携するための「手合図」や「笛の合図」の方法を学び、その重要性を体感します。
講習に必要な法定時間と一般的な日数
この特別教育の講習時間は、労働安全衛生法によって厳密に定められています。学科と実技を合わせて、合計で13時間以上の教育を行う必要があります。
具体的な時間配分は以下の表の通りです。
| 講習区分 | 科目 | 法定時間 |
|---|---|---|
| 学科講習 | クレーンに関する知識 | 3時間 |
| 原動機及び電気に関する知識 | 3時間 | |
| 運転のために必要な力学に関する知識 | 2時間 | |
| 関係法令 | 1時間 | |
| 実技講習 | クレーンの運転 | 3時間 |
| 運転のための合図 | 1時間 | |
| 合計 | 13時間 |
この法定時間を満たすため、ほとんどの講習機関では2日間の日程でカリキュラムが組まれています。1日目に学科、2日目に残りの学科と実技、といった形で進められるのが一般的です。
受講費用と資格条件について
床上操作式クレーン運転特別教育を受けようと考えたとき、気になるのが「費用はいくらかかるのか」「誰でも受講できるのか」という点でしょう。ここでは、受講に必要な費用と、活用できる可能性のある助成金制度、そして受講資格について解説します。
費用の相場と活用できる助成金制度
特別教育の受講費用は、講習を実施する機関によって多少異なりますが、おおむね1万5千円から2万円程度が一般的な相場です。この金額には、講習料のほかに、使用するテキスト代や、教育を修了したことを証明する修了証の発行手数料などが含まれている場合がほとんどです。
もし、会社からの指示で受講する場合、費用は会社が負担してくれるケースが多いでしょう。さらに、事業主が費用を負担して従業員に教育を受けさせる際には、国からの助成金制度を利用できる可能性があります。
代表的なものに、厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金」があります。これは、従業員のスキルアップを支援する企業に対して、かかった経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。利用には一定の条件がありますが、企業の負担を大きく軽減できるため、会社の総務や人事担当の方に一度確認してみることをお勧めします。
なお、人材開発支援助成金をはじめ、特別教育・安全衛生教育で使える補助金・助成金制度については、こちらの記事で詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
受講に必要な年齢などの条件
この特別教育を受講するにあたって、特別な学歴や実務経験は一切必要ありません。クレーンに関する知識が全くない状態からでも、安心して受講することができます。
ただし、年齢に関しては注意が必要です。法律上、クレーン運転のような危険を伴う業務に18歳未満の者を就かせることは禁止されています(労働基準法)。このため、ほとんどの講習機関では、受講資格を「満18歳以上」と定めています。
まとめると、受講の条件は非常にシンプルです。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 学歴・経験 | 不問 |
| 年齢 | 満18歳以上であること |
この条件を満たしていれば、誰でも特別教育を受講し、安全なクレーン作業者への第一歩を踏み出すことが可能です。
【最重要】「玉掛け」資格との関係性を正しく理解する
クレーン作業の安全を考える上で、この「玉掛け」という資格との関係を理解することは、他のどの知識よりも重要だと言っても過言ではありません。クレーンを運転する資格さえあれば、すべての作業ができると思われがちですが、それは大きな誤解です。ここでは、安全な作業に直結する両者の関係性を、分かりやすく解説します。
クレーン「運転」と荷を「掛ける」作業は全く別の資格
まず、大原則として覚えていただきたいのは、クレーンを「運転する資格」と、そのクレーンのフックに荷物を「掛けたり、外したりする資格」は、法律上、全くの別物であるということです。
- 床上操作式クレーン運転特別教育: クレーン本体を操作し、荷物を上げ下げしたり、水平に移動させたりするための資格です。
- 玉掛け技能講習(または特別教育): ワイヤーロープなどの吊り具を用いて、荷物をクレーンのフックに安全に掛ける、または外す作業(玉掛け作業)を行うための資格です。
つまり、どれだけクレーンの運転が上手くても、「玉掛け」の資格がなければ、荷物をフックに掛ける作業に従事することは法律で認められていません。逆に、玉掛けの資格だけを持っていても、クレーンの運転はできません。この二つは、安全なクレーン作業を支える、車の両輪のような存在なのです。
なぜ多くの現場で両方の資格が求められるのか
実際の工場や倉庫の作業現場を想像してみてください。多くの場合、クレーンを運転する人が、自分自身で荷物にワイヤーを掛け、フックにセットし、そしてクレーンを操作して運搬するという一連の作業を一人で行っています。
このように一人の作業者がクレーン運転と玉掛け作業の両方を担当する場合、その作業者は当然、両方の資格を持っている必要があります。どちらか一方の資格しか持たずに作業を行うことは、明確な法律違反となります。
企業側から見ても、作業効率や人員配置の柔軟性を考えると、一人の従業員が両方の作業を行えることが望ましいのは明らかです。そのため、求人募集の際に両方の資格を必須条件としたり、入社後に両方の資格取得を推奨・義務付けたりする企業が非常に多いのです。
クレーン作業と玉掛け作業は、安全な揚重作業に不可欠なペア業務です。クレーン運転者が玉掛け作業を兼務する場合だけでなく、専任の玉掛け作業者と連携する場合でも、その役割と責任を理解しておくことが重要です。玉掛け作業者の安全を守るための玉掛け業務従事者安全衛生教育というものもあり、管理者やクレーン運転者もその内容を知っておくと、より安全な現場づくりに繋がります。
セットで効率よく取得できる講習コースのメリット
このような現場の実情に合わせて、多くの教習機関では「床上操作式クレーン運転特別教育」と「玉掛け技能講習」を組み合わせた、セットコースを用意しています。
これから資格を取ろうと考えている方にとって、このセットコースには大きなメリットがあります。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 費用の割引 | それぞれの講習を個別に申し込むよりも、セット料金として割安に設定されていることが多いです。 |
| 日数の短縮 | 連続した日程で講習が組まれているため、効率よく、短期間で両方の資格を取得できます。 |
| 手続きの手間削減 | 申し込み手続きが一度で済むため、手間を省くことができます。 |
| 知識の相乗効果 | クレーンと玉掛けの知識を連続して学ぶことで、安全な作業への理解がより一層深まります。 |
もしあなたが、これからクレーン作業に従事する予定で、どちらの資格も持っていないのであれば、このセットコースの受講を強くお勧めします。時間と費用の両面で、最も合理的で賢い選択と言えるでしょう。
なお、クレーン作業に不可欠な玉掛け業務やその後の安全衛生教育については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
他のクレーン関連資格との違いを整理
クレーンに関する資格には、「床上操作式クレーン運転特別教育」のほかにも、似たような名前のものがいくつか存在します。特に、現場でよく耳にする「小型移動式クレーン」の資格とは混同されやすいため、その違いをここで明確にしておきましょう。自分が本当に必要な資格を正しく選ぶための、重要な知識です。
小型移動式クレーン運転技能講習との操作対象の違い
「小型移動式クレーン運転技能講習」は、その名の通り「移動式クレーン」を操作するための資格(技能講習)です。
では、「移動式クレーン」とは何でしょうか。これは、トラックの荷台にクレーンが架装された、いわゆる「ユニック車」や「トラッククレーン」のように、それ自体が公道を走行するなどして不特定の場所へ移動できるクレーンを指します。
一方で、これまで解説してきた「床上操作式クレーン」は、工場や倉庫の天井などにレールが設置され、その上を動く「定置式」のクレーンです。
| 項目 | 床上操作式クレーン | 小型移動式クレーン |
|---|---|---|
| 設置形態 | 定置式(工場や倉庫の天井などに固定) | 移動式(トラックなどに搭載) |
| 主な作業場所 | 屋内の決まった場所 | 屋外を含む、不特定の場所 |
| 必要な資格 | 床上操作式クレーン運転特別教育 (5t未満) | 小型移動式クレーン運転技能講習 (5t未満) |
このように、操作するクレーンの種類が根本的に異なります。あなたが職場で扱うクレーンが、建物の一部として設置されているものなのか、それとも車両に搭載されて移動するものなのかをしっかりと確認し、間違えないようにしましょう。
もし、あなたが扱うクレーンがトラックに搭載されているタイプであれば、必要なのは「小型移動式クレーン運転技能講習」です。資格の名前は似ていますが、全くの別物ですので、申し込みの際には十分にご注意ください。
どの資格を取るべき?目的別の資格選び早見表
ここまで解説してきた各種資格について、「どんな作業をしたいか」という目的別に整理しました。この表を見れば、あなたが今、どの資格を取得すべきかが一目で分かります。
| こんな作業がしたい(目的) | 取得すべき資格・教育 |
|---|---|
| 工場の天井にある、手元ボタンで操作するクレーン(5t未満)を運転したい | 床上操作式クレーン運転特別教育 |
| クレーンのフックに、ワイヤーなどで荷物を掛けたり外したりする作業がしたい | 玉掛け技能講習 |
| ユニック車やトラッククレーン(5t未満)を運転・操作したい | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
| 5トン以上の大きな床上操作式クレーンを運転したい | 床上操作式クレーン運転技能講習 |
| 5トン以上のクレーン全般(無線式含む)やデリックを運転したい | クレーン・デリック運転士免許(国家資格) |
この表を参考に、ご自身の業務内容や将来のキャリアプランと照らし合わせて、取得する資格の目標を定めてみてください。どのクレーンを運転する場合でも、荷物をフックに掛ける作業が伴うのであれば、「玉掛け」の資格も合わせて必要になることを忘れないようにしましょう。
受講の申し込みから修了証取得までの流れ
さて、受講する資格が決まったら、次はいよいよ実際の申し込みです。ここでは、講習機関を探すところから、無事に修了証を手にするまでの具体的なステップを、順を追って解説していきます。一つひとつの手順をしっかり確認して、スムーズに準備を進めましょう。
講習機関の探し方と選び方のポイント
床上操作式クレーン運転特別教育は、全国の様々な機関で実施されています。主な講習機関は以下の通りです。
- 各都道府県の労働基準協会連合会
- コベルコ教習所やコマツ教習所といった、大手建機メーカー系の教習センター
- 地域に根差した民間の登録教習機関
これらの機関は、インターネットで「お住まいの地域名 床上操作式クレーン 特別教育」や「〇〇県 クレーン 講習」といったキーワードで検索すれば簡単に見つけることができます。
たくさんの講習機関が見つかると思いますが、選ぶ際には以下のポイントを比較検討することをお勧めします。
- アクセスのしやすさ: 自宅や職場から通いやすい場所にあるか。公共交通機関で行けるか、駐車場はあるかなどを確認しましょう。
- 開催日程: 自分の仕事のスケジュールに合う日程で講習が開催されているか。土日に開催している機関もあります。
- 費用: 受講料やテキスト代を含めた総額が、相場と比べてどうか。
- セット講習の有無: もし玉掛けの資格も一緒に取得したい場合は、「クレーン・玉掛けセットコース」がある機関を選ぶと、時間も費用も節約できます。
申し込み手続きと事前に準備するもの
受講したい講習機関と日程が決まったら、申し込み手続きに進みます。多くの場合、ウェブサイトの申し込みフォームか、電話で予約をした後、送られてくる申込書を郵送またはFAXで提出する流れとなります。申し込みが受理されると、受講料の振込案内などが届きますので、期日までに支払いましょう。
講習当日に慌てないよう、事前に準備しておくべきものをリストアップしました。機関によって若干の違いはありますが、一般的に以下のものが必要となります。
| 持ち物の種類 | 具体的な内容・注意点 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的な身分証明書。 |
| 受講票・申込書控 | 郵送で送られてきた場合や、ウェブで印刷した場合に持参します。 |
| 筆記用具 | 学科講習でメモを取ったり、試験を受けたりするために必須です。 |
| 証明写真 | 修了証に貼付するための顔写真です。サイズ(例:縦3.0cm×横2.4cm)が指定されていることが多いので、案内をよく確認しましょう。 |
| 実技に適した服装 | 長袖・長ズボンが基本です。作業の妨げになるような服装は避けましょう。 |
| 安全装備 | 安全靴やヘルメット、手袋(軍手など)は、持参を求められることが多いです。貸し出しの有無も確認しておくと安心です。 |
| 受講費用 | 当日現金払いの場合に必要です。 |
講習当日の流れと心構え
いよいよ講習当日です。2日間の講習は、法律で定められた時間を満たさなければ修了とは認められません。遅刻や早退は厳禁ですので、時間に余裕を持って会場へ向かいましょう。
一般的な当日の流れは以下のようになります。
- 受付: 会場に到着したら、まず受付で本人確認を済ませます。
- 学科講習: テキストが配布され、講師による講義が始まります。眠くならないよう、自分の安全を守るための大切な知識だと意識して、真剣に耳を傾けましょう。
- 実技講習: ヘルメットなどを装着し、実際のクレーンを使って操作練習を行います。最初は緊張するかもしれませんが、講師が安全に配慮しながら丁寧に教えてくれます。わからないことは、その場で積極的に質問しましょう。
- 修了試験: 講習の最後には、学んだ内容の理解度を確認するための簡単な学科試験が行われることがほとんどです。講習をしっかり聞いていれば、問題なく解答できる内容です。
- 修了証の交付: 試験に合格すれば、その日のうちに写真付きの修了証が交付されます。これであなたも、正式にクレーンを運転できる資格を得たことになります。
この修了証は、運転免許証と同じくらい大切なものです。紛失しないよう、大切に保管してください。
床上操作式クレーン運転特別教育に関するよくある質問
ここでは、床上操作式クレーン運転特別教育の受講を検討している方々から、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。受講前のちょっとした疑問や不安を、ここで解消しておきましょう。
試験は難しい?合格率はどのくらい?
「講習の最後に試験があると聞いたけれど、難しいのだろうか」「もし落ちてしまったらどうしよう」といった不安を感じる方は少なくありません。
結論から言うと、過度に心配する必要はありません。この教育の最後に行われる試験は、受講者をふるいにかけるためのものではなく、あくまで「講習内容をきちんと理解できたか」を確認するためのものです。
そのため、講習中に講師の話を真面目に聞いていれば、ほとんどの方が問題なく合格できる内容になっています。合格率を公表している機関は多くありませんが、一般的には非常に高い水準にあると言われています。万が一、試験の点数が基準に満たなかった場合でも、多くの講習機関ではその場で補習や追試といった対応をしてくれるため、不合格になって修了証がもらえない、ということは滅多にありません。大切なのは、講習に真剣に取り組む姿勢です。
資格に有効期限や更新手続きは必要?
一度取得した資格が、いつの間にか失効してしまっていたら大変です。この点についてもご安心ください。
床上操作式クレーン運転特別教育の修了証には、自動車の運転免許証のような有効期限は設けられていません。したがって、定期的な更新手続きも一切不要です。一度、この教育を修了すれば、その資格は生涯にわたって有効となります。
ただし、修了証を紛失したり、損傷したりした場合には、再発行の手続きが必要です。また、結婚などで氏名が変わった際にも、書き換えの手続きを行う必要があります。手続きは、講習を受けた機関で行うのが一般的ですので、万一の際には受講した機関に問い合わせてみましょう。
履歴書の資格欄への正しい書き方
無事に修了証を取得したら、それはあなたの立派なスキルの一つです。就職や転職の際には、履歴書の資格欄に忘れずに記載しましょう。
その際、どのように書けば良いか迷うかもしれませんが、以下の例のように正式名称で書くのが基本です。
履歴書への記載例
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 令和〇〇 | 〇 | 床上操作式クレーン運転特別教育 修了 |
「取得」ではなく「修了」と書くのがポイントです。また、もし玉掛けの資格も合わせて取得した場合は、以下のように並べて記載すると良いでしょう。
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 令和〇〇 | 〇 | 床上操作式クレーン運転特別教育 修了 |
| 令和〇〇 | 〇 | 玉掛け技能講習 修了 |
これらの資格は、製造業や物流業など、多くの業界で高く評価されます。自信を持ってアピールしましょう。
まとめ:安全なクレーン作業者としての一歩を踏み出すために
これまで、床上操作式クレーン運転特別教育について、その基本から具体的な講習内容、そして「玉掛け」との重要な関係性までを詳しく解説してきました。
この教育は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンを安全に扱うための、法律で定められた第一歩です。2日間程度の講習で、安全な作業に不可欠な知識と技術を体系的に学ぶことができます。
特に繰り返しお伝えしたいのは、「クレーンを運転する資格」と「荷物を玉掛けする資格」は全く別物であるという点です。実際の現場では両方の作業を一人で行う場面が非常に多く、両方の資格を持つことが、自身の安全を守り、仕事の幅を広げる上で極めて重要になります。これから資格取得を目指す方は、ぜひ「玉掛け」とのセット受講を検討してみてください。
この記事が、あなたの新たなスキル習得への不安を解消し、安全なクレーン作業者としての確かな一歩を踏み出すためのお役に立てたなら幸いです。
参考URL
この記事を作成するにあたり、以下の公的なウェブサイトの情報を参考にしました。法律の原文や、国が発信する安全情報、助成金制度の詳細などを確認する際にご活用ください。
- e-Gov法令検索|クレーン等安全規則 本記事で解説した特別教育の根拠となる法律の条文を、原文で確認することができます。デジタル庁が提供する法令データ提供システムです。
- 職場のあんぜんサイト|厚生労働省 厚生労働省が運営する、労働安全衛生に関する総合情報サイトです。労働災害事例や、安全衛生に関する法令・通達などを検索できます。
- 一般社団法人 日本クレーン協会 クレーン業界を代表する公的な団体です。各種資格や講習に関する公式情報がまとめられています。
- 人材開発支援助成金|厚生労働省 企業が従業員に教育を受けさせる際に利用できる、助成金制度の公式ページです。支給要件や申請手続きなどを確認できます。